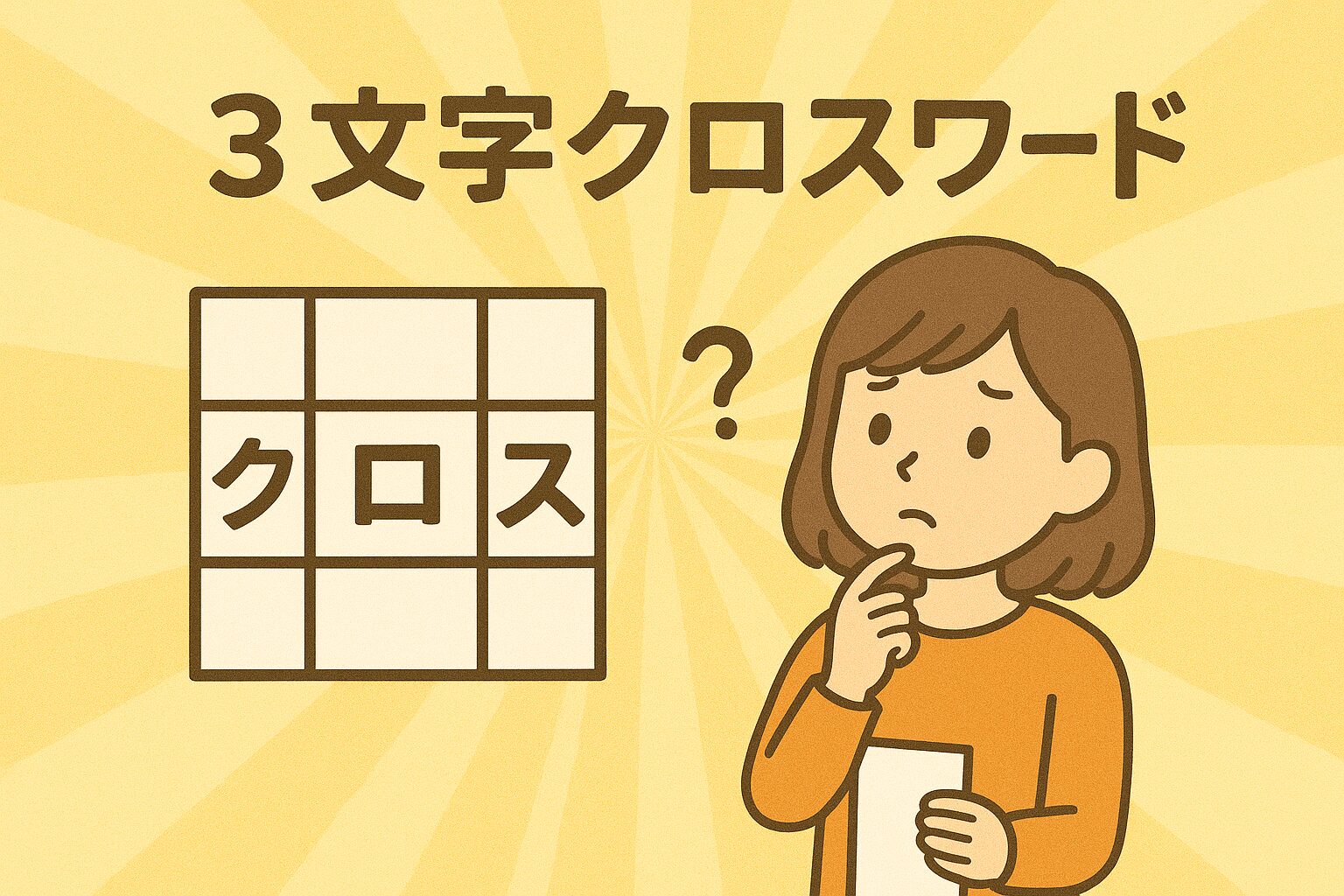はじめに
「高齢になったら運転はいつまで続けてもいいのかな?」
そんな不安を抱える方やご家族も多いと思います。でも、大丈夫。運転を安心して続けるために、ポイントを押さえてゆっくり一緒に考えていきましょう。
1. 運転中の事故、中でも高齢者はどうなってるの?
- 2024年、日本の交通事故による死者は 2,663人 で、前年より15人減りましたが、高齢者(65歳以上)の死者数は 1,513人と 47人増加。高齢者が占める割合は全体の **約56.8%**と高い水準が続いています (Nippon大阪ガスオートサービス)
- さらに、交通事故死者・重傷者とも減少傾向ですが、65歳以上の死者数は 前年比3.2%増となっています (警察庁Nippon)
- 注意すべきは、「単独車事故」が高齢ドライバーに多く見られる点。特に男性では80歳以上、女性では75歳以上で事故率が明らかに高くなる傾向があります (国際交通安全学会)
近年では、高速道路の逆走なども見られており話題になっています。日常が安全であり続けるよう、運転能力を定期的に見つめ直すのが大切です。
2. 法律や検査制度、どうなってるの?
- 75歳以上の方は、免許更新の際に 認知機能検査と 高齢者講習が必須です 。
- もし違反歴がある場合は、さらに 運転技能検査も必要になります
- さらに、認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された場合、たとえ違反がなくても 医師の診断書の提出か 運転をやめる 判断が求められます。
- この制度強化により、過去より多くの方に高齢者講習ときめ細かな対応が行われ、年間で数十万人が対象となっている見込みです 。今後も今後も有免者は増えていく見込みです。
こうした制度は、安全に運転を続けられるよう、本人と周囲を支える大切なしくみになっています。
心配な方は、警察庁のサイトにて認知機能検査の用紙をダウンロードし試しに実施することもできます。当サイトでも認知機能の模擬的なプリントをダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
3. 準備の目安—「そろそろかな?」と思ったら
以下のようなことが増えてきたら、ちょっと立ち止まって考えてみるサインかもしれません:
- 信号や標識が見えづらいと感じる
- 駐車が前より時間がかかる
- 運転すると強く疲れるようになった
- 家族から「大丈夫かな?」と声をかけられた
- 単独事故や不安な経験が増えてきた
これらを感じたら、まずは高齢者講習や運転適性相談を活用するのが安心です
4. 「運転やめたらどうしよう…」の不安を和らげるには?
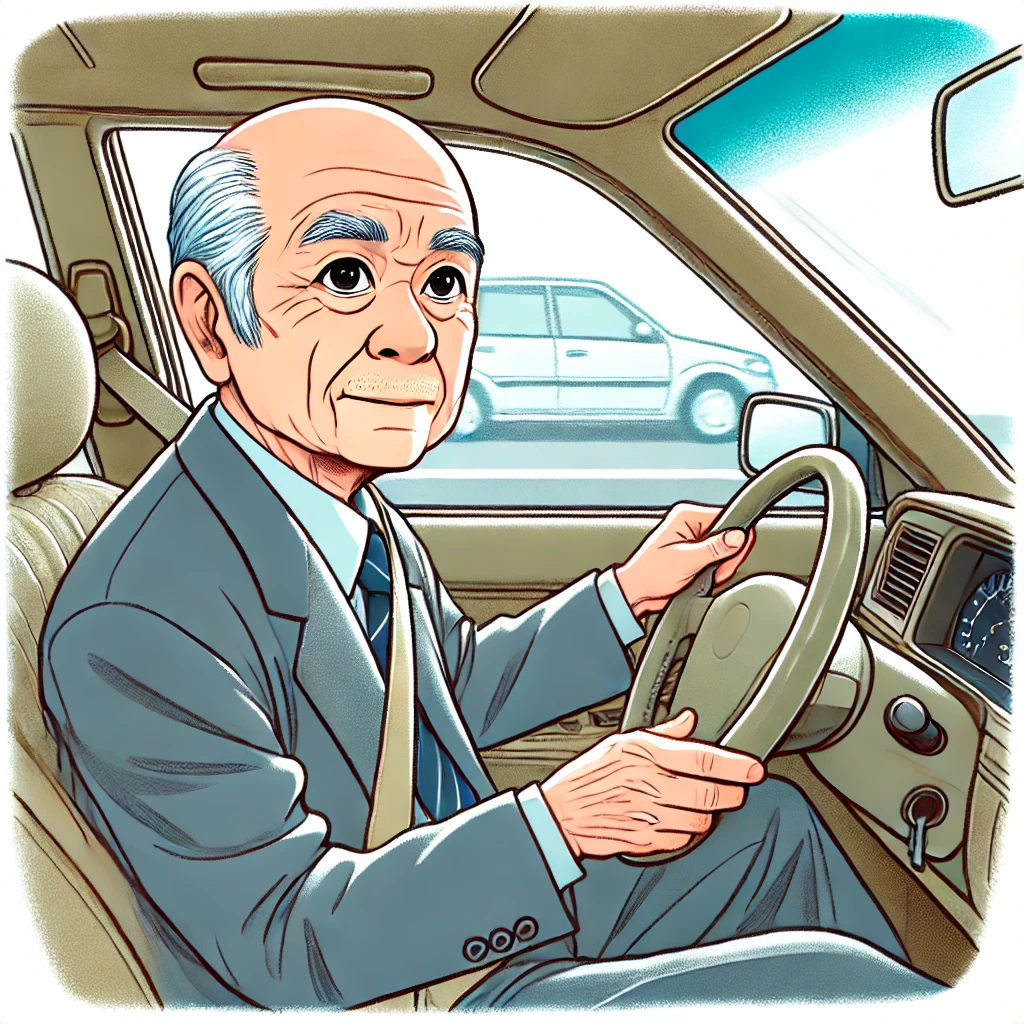
「車がないと生活が大変」と感じるのは自然なことです。でも、近年はサポート体制も少しずつ整ってきています:
- 地域のバス・コミュニティ送迎サービス
- 買い物や通院の宅配サービス
- 免許返納者向けの補助や割引制度
免許を返納する際は、一気に切り替えるよりも、段階を踏んで代替手段に触れておくと移行がスムーズです。ただし、各制度には地域差も認められます。都市部と地域とでは車の必要性や、交通機関などのインフレ整備などの違いもあります。その地域に合わせて考えなければいけないと思われます。